トイレをリフォームしたいけど、気になるのはやっぱり「費用」ですよね。
とくに最近は、物価上昇や工事単価の高騰もあり、「できるだけ安く済ませたい」と感じる方が増えています。
そんなときに知っておきたいのが、トイレ工事に使える補助金制度です。
実は国や自治体によって、条件を満たせば数万円〜十数万円の補助を受けられるケースも少なくありません。
とはいえ、「そもそもどんな工事が補助対象になるのか?」「申請の流れは?」「自宅でも使えるの?」といった疑問が多く、制度の内容が分かりづらいのも事実です。
この記事では、そんな不安を解消するために、
- トイレ工事で補助金が使えるケースと金額の目安
- 対象になりやすい工事内容(和式→洋式・手すり設置・2階増設など)
- 補助金の申請方法と注意点
- よくある質問や失敗例
などをわかりやすく解説していきます。
うまく活用すれば、トイレ工事の自己負担をグッと抑えることも可能です。
後悔しないリフォームのために、ぜひ事前にチェックしておきましょう。
トイレリフォーム・増設に使える助成金や補助金は?仕組みをわかりやすく解説
国・自治体の補助金制度の基本的な考え方
トイレリフォームに関する補助金は、国だけでなく、各自治体が独自に実施している制度も数多くあります。
全国共通で使える制度もありますが、多くは自治体ごとに「対象者」や「工事内容」、「補助金額」などが異なるため、お住まいの地域の制度を個別に確認することが重要です。
主な制度には、以下のようなものがあります。
- 介護保険の住宅改修費補助(全国共通):バリアフリー化工事を対象に、最大20万円の補助(1〜3割負担)
- 各市町村の住宅リフォーム補助制度:省エネ設備への交換や和式から洋式への変更、2階トイレの増設などを支援
- 高齢者・障がい者住宅改修支援:安全性や生活利便性を目的としたリフォームを支援するケースが多い
こうした補助金は基本的に「工事前に申請」が原則なので、申請手続きは必ず業者選定より前に進める必要があります。
制度の詳細は自治体のホームページや役所の窓口で確認できます。
補助金と助成金・減税制度の違いとは?
トイレ工事に関する支援制度には、「補助金」だけでなく「助成金」「減税制度」などもあります。
それぞれ仕組みが異なるため、違いを理解しておくと制度選びや併用の判断に役立ちます。
| 種類 | 特徴 | 代表例 |
|---|---|---|
| 補助金 | 予算に限りがあり、事前申請制。条件を満たす必要あり。 | 自治体の住宅リフォーム補助、国の補助金制度など |
| 助成金 | 条件を満たせば原則もらえる。補助金よりハードルが低い場合あり。 | 介護保険の住宅改修、障がい者支援など |
| 減税制度 | 所得税・固定資産税の軽減。確定申告が必要な場合が多い。 | バリアフリー減税、住宅ローン控除など |
実際のリフォームでは、補助金+減税を併用できる場合もあります。
たとえば、「介護保険の住宅改修+バリアフリー減税」のような組み合わせで、補助と税控除の両方を活用することも可能です。
なお、制度の活用方法や併用の可否は、自治体窓口やリフォーム業者でも案内してもらえるので、迷ったら早めに相談してみると良いでしょう。
このように、「トイレ工事=全額自己負担」と思われがちですが、制度を理解し活用すれば、費用を大幅に抑えられる可能性があります。
🟦 【PR】水回りリフォーム、どこに頼むか迷っていませんか?
「信頼できる業者を探したい」「相場が分からない」そんな方におすすめなのが、
👉 リショップナビの無料一括見積もりです。
全国の厳選された優良業者のみを比較できて、しつこい営業もなし。
完全無料で使えるので、まずは相場を知るだけでもOKです。

どんなトイレ工事が補助金の対象になる?よくあるパターンを紹介
和式から洋式への交換工事
多くの自治体が補助対象としている代表的な工事が、和式トイレから洋式トイレへの変更です。
これは、高齢者や体の不自由な方にとって安全性・快適性を高めるための改修とされ、介護保険や自治体のバリアフリー支援の対象になりやすいのが特徴です。
補助の一例
- 工事費の2〜9割補助(条件により負担割合が異なる)
- 上限10万〜20万円程度が一般的
- 工事前申請が必須。写真・図面・見積書が必要なことが多い
なお、便器本体の交換だけでなく、段差解消や内装(床・壁)の一部改修費も対象に含まれるケースが多いため、リフォーム全体のコストを抑えやすいメリットもあります。
【関連記事:和式から洋式への交換補助金まとめ】
▶ トイレを和式から洋式に補助金で交換するには?
手すりや段差解消などのバリアフリー工事
トイレのバリアフリー化も、補助金対象として非常に多い項目です。
特に介護保険の住宅改修制度では、以下のような内容がカバーされています。
- 壁面への手すりの取り付け
- 床の段差の解消(スロープ化やバリアフリー床材への変更)
- ドアの開閉しやすさ向上(引き戸化など)
制度の概要:
- 上限20万円(自己負担1〜3割)
- 要介護・要支援認定を受けている方が対象
- 支給は1回のみだが、引っ越しや症状変化により再利用できる場合あり
これらの工事は、転倒防止や自立支援の観点から自治体も積極的に推奨しています。
【関連記事:高齢者向けトイレリフォームと補助金】
▶ 高齢者向けトイレリフォームに使える補助金とは?
【関連記事:手すりの取付と補助金まとめ】
▶ トイレの手すり取り付け費用はいくら?
トイレの新設・増設(2階・離れなど)
「2階にもトイレを増やしたい」「離れに簡易トイレを設置したい」といったトイレの増設・新設工事も、条件を満たせば補助対象になることがあります。
代表的な対象例:
- 夜間の階段移動を避ける目的での2階増設
- 高齢者が1階で生活しやすくするための簡易水洗設置
- 多世帯同居で混雑を避けるためのサブトイレ設置
制度によっては「生活改善目的」「高齢者支援目的」などの条件がついていますが、最大30万円前後の補助が受けられる自治体もあります。
【関連記事:2階へのトイレ増設と補助金】
▶ 2階にトイレを増設するには?
このように、補助金が適用される工事は「便器の交換」だけでなく、「周辺の安全対策」や「生活改善につながる増設」まで幅広く存在します。
高齢者・障がい者向けトイレリフォームに使える主な補助金制度
介護保険の住宅改修費支給制度
要支援・要介護認定を受けた高齢者がいる世帯では、介護保険の住宅改修費支給制度を利用することで、トイレのバリアフリー化にかかる費用の一部を補助してもらえます。
対象となる工事例は以下の通りです。
- 和式トイレから洋式トイレへの変更
- 手すりの設置
- 段差の解消
- 滑りにくい床材への変更
- 開き戸を引き戸に交換する工事 など
この制度では、最大20万円の工事費用に対して、その7~9割(1~3割自己負担)を補助してもらえます。
原則として1人につき1回限りの利用となりますが、引っ越しや要介護状態の大きな変化があれば再度利用できるケースもあります。
制度の利用には、事前申請が必須です。ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて、自治体へ申請し、承認を受けたうえで工事を行います。
障がい者自立支援法による住宅改修助成
障害者手帳を持っている方を対象に、住宅のバリアフリー改修に対する助成を行っている自治体も多くあります。
これは「障がい者自立支援法」や、地方自治体の障がい福祉施策に基づく支援であり、トイレの改修も対象範囲に含まれます。
具体的な助成対象となる工事には、以下のようなものがあります。
- 車いす使用を前提としたトイレスペースの拡張
- 手すりの取り付けや便器の高さ調整
- 自動洗浄やセンサー付き便座の導入 など
助成金額の上限や対象内容は自治体によって異なり、10万~50万円程度の範囲で設定されていることが多いです。
また、所得制限が設けられている場合もあるため、必ずお住まいの自治体の窓口で確認してください。
この制度も事前申請が必要で、書類の提出や福祉担当者との面談が求められるケースがあります。
自治体独自のバリアフリー・住宅改修支援
介護保険や障がい者向け制度とは別に、各市区町村が独自に提供している住宅改修の補助制度も見逃せません。
多くの自治体では、高齢者・障がい者に限定せず、広く住宅のバリアフリー化や安全性向上を目的としたリフォームに対する支援を行っています。
代表的な支援内容には以下のようなものがあります。
- トイレの洋式化・節水型トイレへの交換
- 手すり・段差解消などの安全対策
- 断熱性・省エネ性能を高める設備の導入 など
補助率は工事費用の10〜50%、上限額は10万円〜30万円程度が一般的です。
なかには地域活性化や移住支援の一環として補助を手厚くしている自治体もあります。
こうした制度は年度ごとに募集期間や内容が変わることもあるため、以下の方法で情報収集するのがおすすめです。
- 自治体のホームページ「住宅支援」「バリアフリー改修」ページをチェック
- 地元のリフォーム業者に問い合わせる(制度に詳しい場合あり)
- 地域包括支援センターや福祉窓口で相談する
このように、高齢者・障がい者を対象とした補助金制度は多岐にわたり、複数の制度を組み合わせて活用できる場合もあります。
ただし、どの制度も「工事前の申請」が原則なので、補助を受けたい場合は早めの情報収集と準備が重要です。
補助金の申請方法と流れを徹底解説
申請前に確認すべき条件や書類
補助金を活用してトイレ工事を行う場合、申請前の準備が非常に重要です。
なぜなら、ほとんどの補助金制度では「工事前に申請が必要」というルールがあるからです。工事後の申請では、いくら条件に当てはまっていても補助が受けられないケースが大半です。
申請前に確認しておくべき主な項目は以下の通りです。
- 対象となる工事内容か(例:バリアフリー化、洋式トイレへの交換など)
- 対象者の条件(年齢、要介護認定の有無、障がい者手帳の有無など)
- 所得制限があるかどうか
- 工事予定日と申請期限の関係
- 必要な書類(申請書、工事見積書、図面、ケアプランなど)
制度によって求められる書類が異なるため、各自治体のホームページや福祉窓口、地域包括支援センターで確認するのが確実です。
工事前に必ず申請すべき理由とよくあるミス
補助金制度の多くは「事前承認制」です。
つまり、「補助の対象となるかどうかを審査したうえで、OKが出てから工事を始めてください」というルールになっています。
ところが、以下のようなミスがよく起こります。
- 補助金の存在を知らずに、すでに工事が完了していた
- 書類が不備のまま提出され、承認が下りる前に工事を始めてしまった
- ケアマネや業者との連携不足で、必要書類の準備が間に合わなかった
こうしたミスを避けるためには、「補助金を使いたい」と決めた時点ですぐに相談することが大切です。
とくに介護保険の住宅改修補助を使う場合は、ケアマネジャーとの連携が必要不可欠です。
自治体・業者・ケアマネの連携でスムーズに進めるコツ
補助金申請をスムーズに進めるには、「誰とどの段階で連携すべきか」を把握しておくことがポイントです。
- ケアマネジャー(要介護認定者が対象の場合)
→ ケアプランの作成、必要書類の取りまとめ、自治体への申請代行をしてくれる場合もあります。 - リフォーム業者
→ 見積書や図面の作成、制度の適用可否のアドバイスなどを行います。
補助金申請に慣れている業者であれば、手続き全体をサポートしてくれることもあります。 - 自治体の福祉窓口・住宅課
→ 必要書類や審査内容の詳細を確認する場です。不明点は直接電話や窓口で相談するのが安心です。
また、「工事は急ぎたいけど補助金も使いたい」といった場合は、一時立替制度(償還払い)の仕組みを活用できるケースもあります。
その場合でも、やはり申請と承認が出てからでないと対象にならないため注意が必要です。
このように、補助金の申請には多くのステップがありますが、関係者としっかり連携しながら進めれば難しくありません。
トイレリフォームで活用できる主な補助金制度まとめ
介護保険の住宅改修費補助
高齢者のトイレリフォームで最も活用されているのが、介護保険の「住宅改修費補助」です。
これは要支援・要介護認定を受けた方が、日常生活を安全に送れるようにするための住宅改修に対し、最大20万円(支給限度額)の工事費用の7〜9割を補助する制度です。
対象となる工事には、次のようなものがあります。
- 和式から洋式へのトイレ交換
- 手すりの設置
- 段差の解消
- 床材の変更(滑りにくい素材へ)
- 引き戸への変更 など
一度限りの制度ではありますが、「要介護度の大きな変化」や「転居」により、再利用できるケースもあります。
申請にはケアマネジャーの作成するケアプランが必要で、必ず工事前に申請・承認を受けることが条件です。
各自治体の住宅リフォーム補助制度
全国の市町村では、独自の住宅リフォーム補助制度を展開している自治体も多くあります。
この制度は、介護保険とは無関係に使える場合があり、特に高齢者・障がい者世帯、子育て世帯を対象に補助率を高く設定しているところもあります。
補助内容の一例は以下の通りです。
- バリアフリー改修(手すり、段差解消、トイレの洋式化など)
- 省エネ化・断熱性向上(節水型トイレの導入など)
- 水回り全体の改修(キッチンや浴室と一体で補助対象となることも)
補助額は5万円〜30万円程度が一般的で、助成率は工事費用の10〜50%程度と幅があります。
ただし、募集時期や予算枠が設けられており、先着順・抽選制などの制限があるケースも多いため、情報の早期チェックが重要です。
その他の活用できる助成・減税制度
トイレリフォームに使える制度は、補助金以外にもいくつかあります。以下のような支援も検討すると良いでしょう。
- バリアフリー改修による固定資産税の減額措置
要件を満たすバリアフリー工事を行った場合、一定期間、**固定資産税の減額(最大1/3)**が適用されることがあります。 - すまい給付金制度(※現在は終了または縮小傾向)
一定の収入以下の世帯が住宅を取得・改修した場合に給付される制度。※終了済みの自治体多数 - 省エネリフォーム支援(国交省・経産省)
節水型トイレや高効率給湯器の導入が対象となる補助金も存在します。
こうした制度は、複数を併用できることもあるため、工事内容に応じて早めに確認しておきましょう。
補助金を使ったトイレ工事の実例と注意点
よくある失敗・トラブルとその原因
補助金制度はとても便利な一方で、手続きの不備や認識のズレによるトラブルも少なくありません。
以下は、よくある失敗のパターンとその原因です。
- 工事後に申請してしまい補助対象外になった
→ 補助金は基本的に「工事前に申請・承認が必要」です。着工してからでは適用できません。 - 書類の不備や記載漏れで審査に時間がかかる
→ 見積書や図面、ケアマネの書類などが不完全なまま出され、差し戻されるケースも多いです。 - 業者が制度に詳しくなく、対応が遅れた
→ 補助金に精通した業者を選ばないと、スムーズに手続きが進みません。 - 申請者の条件(要介護認定や障がい者手帳など)を満たしていなかった
→ 制度ごとに適用条件が異なるため、事前確認が重要です。
申請に成功したケースの具体例
成功事例を見ると、適切な準備とサポート体制が整っていたことが共通点です。
例1:要介護2の母親のため、和式から洋式トイレに交換(介護保険)
- 工事内容:和式便器から洋式便器への変更、手すり設置、段差解消
- 補助金:住宅改修費(20万円の7割:14万円支給)
- ポイント:ケアマネとリフォーム業者が連携し、スムーズに申請完了
例2:身体障がい者のため、車いす対応トイレに改修(障がい者支援制度)
- 工事内容:トイレスペースの拡張、手すり・自動洗浄便器の設置
- 補助金:自治体から最大50万円の補助を受ける
- ポイント:市の福祉課と事前相談を行い、所得制限もクリア
例3:一般世帯が自治体のリフォーム助成でトイレ改修
- 工事内容:古いタンク式トイレを節水型洋式トイレへ交換
- 補助金:地域限定のバリアフリー補助制度で10万円の支給
- ポイント:募集開始直後に申請し、予算枠内で通過
知らないと損する見落としポイント
補助金制度は見落としやすい落とし穴もあります。以下は特に注意しておきたい点です。
- 制度には募集期間・申請期限がある
→ 年度ごとの予算に基づいており、早めの申請が重要です。 - 同一工事に重複して使えない制度もある
→ 介護保険と自治体の補助を併用できないケースも。確認が必要。 - 住宅の所有者名義・居住実態が問われることがある
→ 登記上の所有者が申請者でないと対象外になることもあります。 - 所得制限や世帯構成の条件がある
→ 高所得世帯が対象外になる制度もあるため、事前の要件確認を。 - 補助対象となる工事内容に制限がある
→ 範囲外の設備(収納・照明など)は自己負担になることも。
まとめ|補助金を活用して、賢くトイレ工事を進めよう
補助金活用で得られるメリット
トイレのリフォームや交換工事は、生活の快適さや安全性を高める重要な設備投資です。
その際に補助金を上手に活用できれば、次のような具体的なメリットが得られます。
- 費用負担を大幅に軽減できる(数万円〜最大50万円以上も可能)
- 介護やバリアフリー対応など、必要性に応じた支援が受けられる
- 節水・省エネ設備の導入で光熱費も節約できる
- 税金の軽減や地域独自の支援が受けられることもある
こうした制度を活用することで、単なるリフォームではなく「将来を見据えた安心できる住まいづくり」に繋がります。
まず確認すべきポイントのおさらい
最後に、補助金を使ってトイレ工事を計画するうえで必ず押さえておきたいポイントをまとめておきます。
- 補助金は「工事前の申請」が原則。後からでは間に合わない
- 制度の対象者・対象工事をよく確認すること
- 複数の制度を組み合わせられる可能性もある
- ケアマネ・業者・自治体と早めに連携するのが成功のカギ
- 募集期間や予算上限があるので、早めの行動が重要
また、補助金制度は自治体ごとに内容が異なるため、自分の住んでいる地域の最新情報をチェックすることも忘れずに。

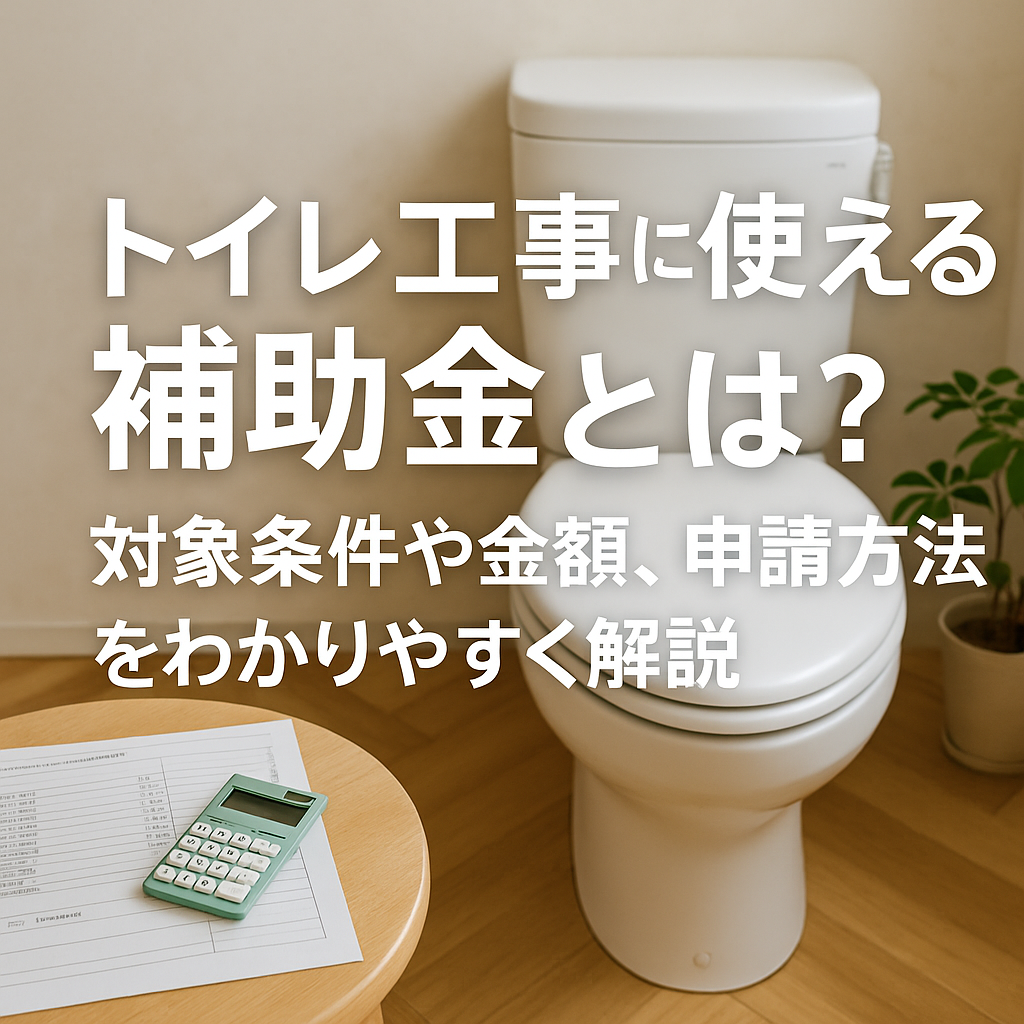
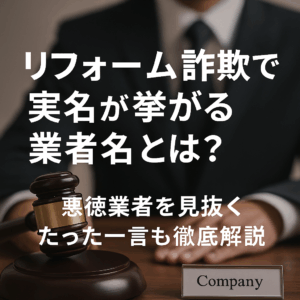
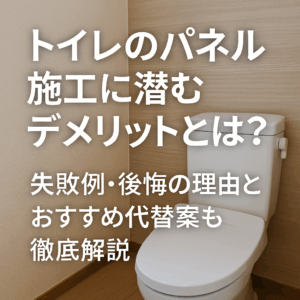
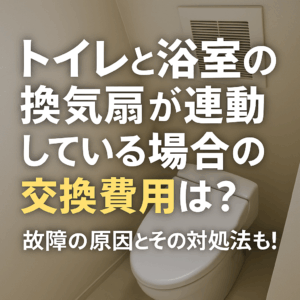
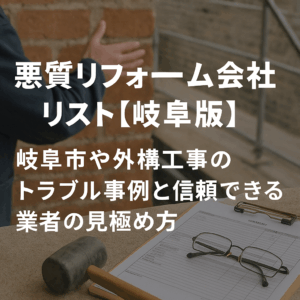
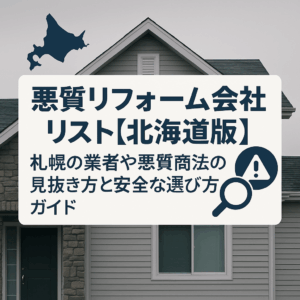

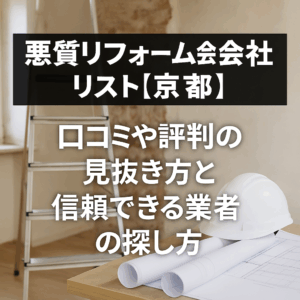
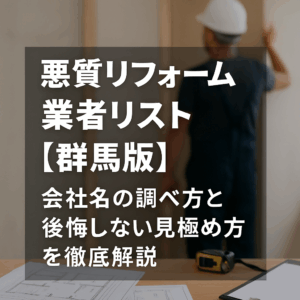
コメント